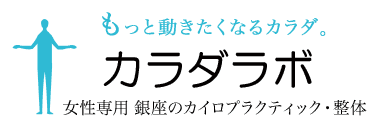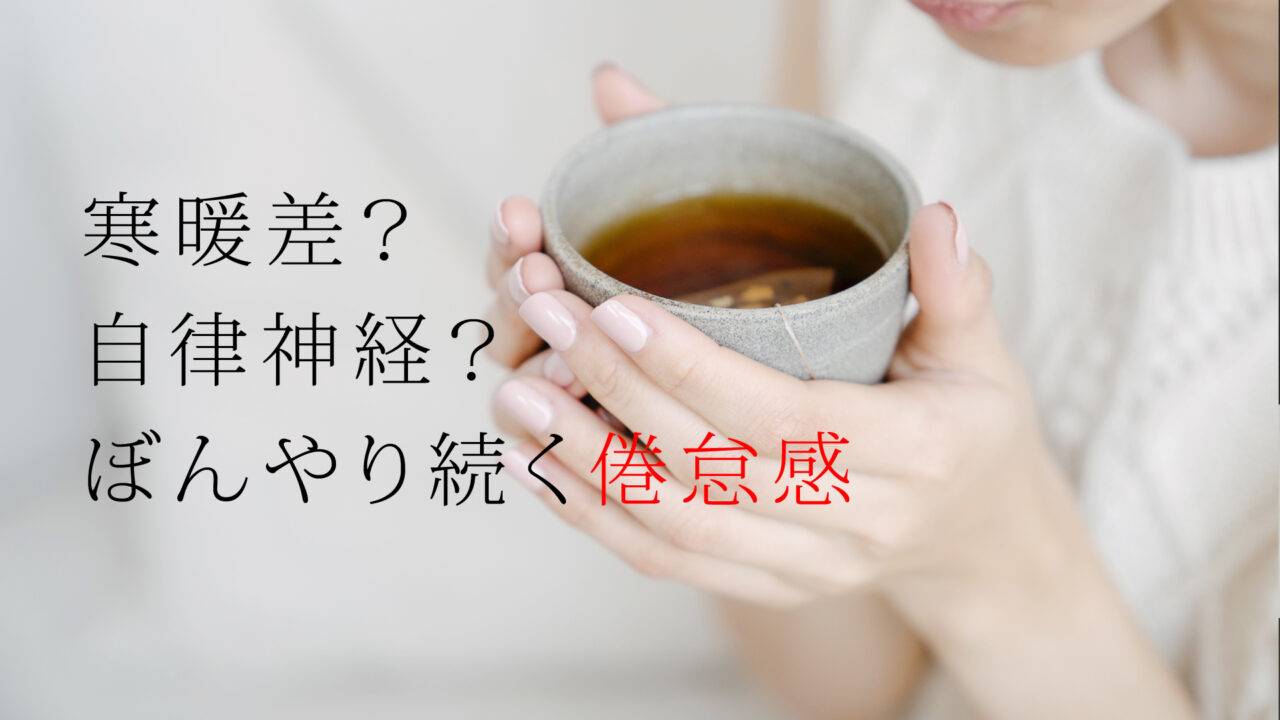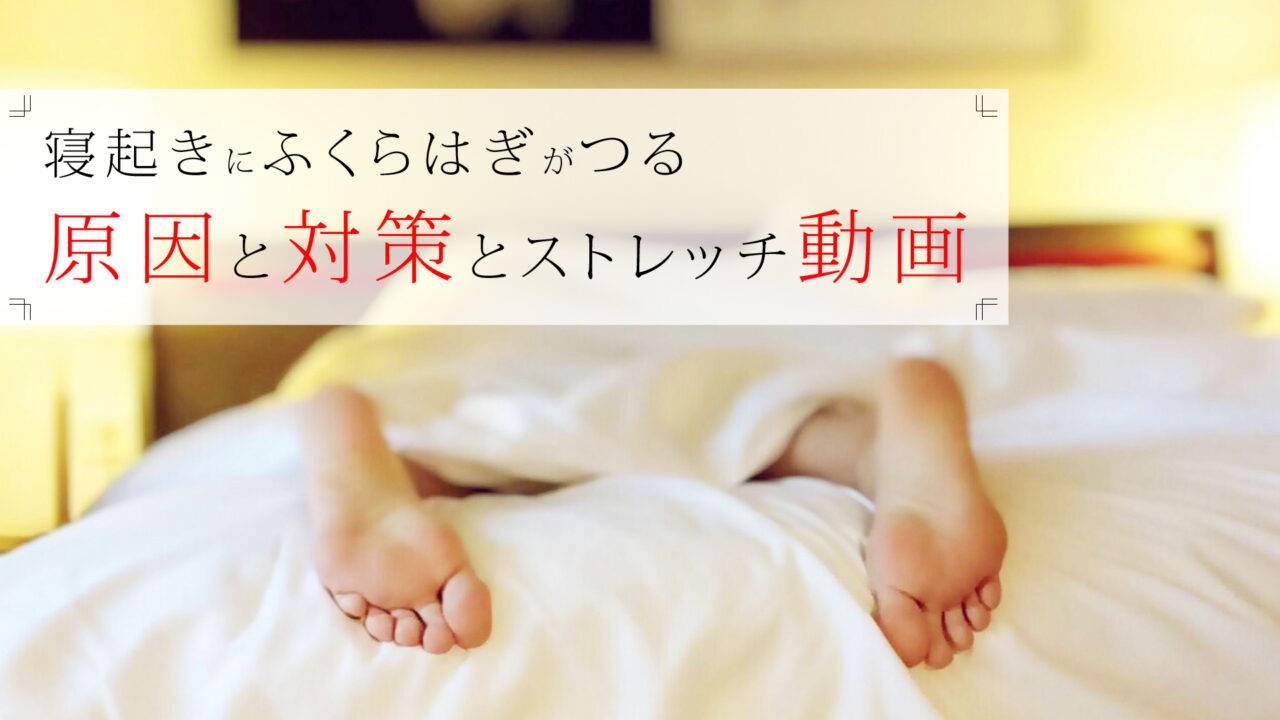季節の変わり目、寒くなるにつれ「骨折」のお話をよく耳にするようになります。
手袋をするにはまだ早いけど手が冷えるからポケットに手を入れる→転倒→骨折や、久しぶりの厚着で体の使い方が慣れない→転倒→骨折などなど、ただでさえ平地でも転倒できるお年頃にさしかかっているため納得の理由です。
特に季節の変わり目は気温や気圧の急激な変動に体がついていけず、体調不良や転倒につながることがあります。
環境的な要因
- 室内での転倒
-
寒さで運動量が減ることや、こたつ布団や暖房器具のコード類の増加、毛足の長い絨毯の使用、寒さ対策で台所などに敷いたマットの端っこぺらめくれやスリップなど、冬特有の室内環境が原因でつまずきやすくなることがあります。
- 厚着と動きの鈍化
-
久しぶりに厚手の服を着ることで体の動きが鈍くなり、バランスを崩して転倒しそうになった時、とっさの対応が遅れてしまい転倒につながることがあります。
- 路面の悪化
-
本格的な冬場になると雪や氷による路面の凍結・積雪で屋外での転倒リスクが大幅に増加します。
また、季節は問いませんが雨天時のマンホール・白線・濡れ落ち葉・散らばってしまったお店の傘ビニール袋・誰が敷いたか大理石っぽい歩道・視認性の悪い階段・歩道植木の柵の無い花壇の段差など注意をするポイントは街中に多く存在します。
身体的な要因
- 骨の健康への影響
-
冬は日照時間が短くなるため、骨の形成に必要なビタミンDの生成が不足しがちになります。これにより、骨の健康維持に影響が出ることが指摘されています。
- 血行不良と筋肉の硬直
-
寒さで血管が収縮し血行が悪くなると筋肉が硬直しやすくなります。これにより体が動かしづらくなり、転倒しやすくなります。
- 運動不足による筋力低下
-
寒さで外出が減り、運動不足になることで筋力が低下しバランス機能も衰えやすくなります。
- 寒暖差による影響
-
急な気温変化によって体が気温の変動に適応できず、血行が悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。 また、寒暖差による血圧の変動も起こりやすく、めまいやふらつきから転倒につながるケースもあります。
- 急な活動量の増減
-
外は寒く、室内は暖かい状態になると急に活動的になり、低下していた筋力や骨の状態を考慮せずに急激に運動を始めるなど活動量を増やすことで、かえって骨折のリスクが高まることがあります。
【まとめ】季節の変わり目の転倒や骨折を避けるには?
季節の変わり目は気温の急変や運動不足による体力の低下などで転倒リスクが高まります。 骨折を予防するためには「体の準備」「生活環境の整備」「骨の強化」の3つの側面から対策を講じることが重要です。
1.体の準備と運動(内的な要因の対策)
急な気温の変化や運動不足による筋力・バランス能力の低下を防ぎます。
| 対策 | ポイント | |
| 筋力・バランス強化 | 下肢筋力とバランス訓練を行う。 | スクワットや片脚立ちを習慣化し、つまずきを防ぐ。不安な場合は壁や椅子に手をついて安全に行う。(片脚立ちは左右1分間ずつが目安) |
| 柔軟性・血行促進 | ストレッチや軽い運動を継続する。 | 特に朝は、寒さで硬くなった筋肉をほぐすために、体を温めてから活動を始めましょう。血行を促進し、ふらつきを予防します。 |
| 日光浴 | 適度に日光を浴びる。 | カルシウムの吸収を助けるビタミンDは、日光を浴びることで皮膚で生成されます。冬でも30分~1時間程度、意識して外に出ましょう。 |
| 体調管理 | 自律神経を整える。 | 季節の変わり目は自律神経が乱れやすいです。ぬるめのお湯にゆっくり浸かる、十分な睡眠をとるなど、規則正しい生活を心がけましょう。 |
| 寒暖差対策 | 衣類で温度調節を徹底する。 | 厚着をするのではなく、重ね着で体温調節をしやすくし、急な寒さや暑さによる体への負担を軽減します。 |
2.生活環境の整備(外的な要因の対策)
室内での転倒事故を防ぐため、足元の危険を取り除きます。
- 「ぬ・か・づけ」に注意!
-
- 「ぬ」
- 濡れているところ(浴室、洗面所、台所など)に滑り止めマットを敷く
- 「か」
- 階段や段差(敷居、カーペットの縁、マットなど)を解消する、または注意を払う
- 「づけ」
- 片づけていないところ(コード類、床に置いた物など)を整理整頓する
- 照明の確保
-
玄関・階段・廊下・夜間のトイレなど暗くなりがちな場所にはセンサーライト(ダイソーなどでも売ってます)などを設置し、足元を明るく保ちましょう。
- 履物
-
室内では滑り止め付きの靴下やスリッパを選び、屋外ではかかとの低い、足にフィットした滑りにくい靴を選びましょう。
3.骨の強化と栄養
骨を丈夫にし骨折しにくい体をつくるための栄養素を意識して摂取します。
| 栄養素 | 働き | 含まれる主な食品 |
| カルシウム | 骨の主成分となる。 | 牛乳、乳製品、小魚、大豆製品、小松菜など |
| ビタミンD | カルシウムの吸収を助ける。 | 鮭、さんま、干ししいたけ、きくらげなど |
| ビタミンK | 骨にカルシウムを沈着させ、骨の形成を促す。 | 納豆、ほうれん草、小松菜、ブロッコリーなど |
| タンパク質 | 骨の土台となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品など |
聞き飽きたフレーズかとは思いますが「バランスの良い食事」を心がけ、特にこれらの栄養素を積極的に摂るようにしましょう。
これらの対策を季節の変わり目だけでなく、日々の習慣として続けることが転倒・骨折予防に繋がります。
とはいえ骨折は状況により避けようと心掛けていても避けられない場合も多いかと思いますがカイロプラクティックは折れてしまっては手出しができません。
骨折の場合は適応外ですので激痛・腫れがひどい場合はすぐに医療機関を受診して下さい。
(余談)
数年前、観光で来られた中国人の女の子二人が「コケテ、アシイタイヨー」と訪ねてこられました。診てみると通常では見られない方向への曲がり方・腫れ方から折れてるかもなと。
院長:これ折れてるかも。病院行ってまずはレントゲン撮ろっか
女の子:ワタシ知ってるよ!カイロは骨の専門家だから治せる!
院長:折れてたらむーりー
女の子:でも病院は保険証ないから高いよ
院長:置いとくとあなたの友達の足はこのまま曲がったままになるかもよ。ほれ、病院行くよー
と、昭和通り挟んだ救急病院に折れてるっぽいっすと連れてったのは院長。